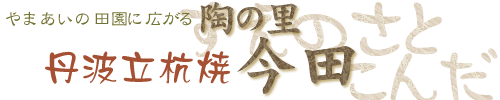
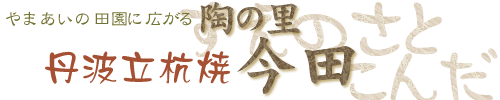 |
|
丹波立杭焼陶磁器共同組合のパンフレットから
当初は、壷やかめ・すり鉢などが主品でしたが、江戸時代前期小堀遠州等の指導により、茶入・水指・茶碗など茶器類に多くの名器を生み、後期には篠山藩の保護育成により、直作(なおさく)、一房(いちふさ)、花遊(かゆう)、一此(いちこの)等の名工が腕を競って、丹波立杭焼の名を高めました。 窯が開かれてからおよそ800年、一貫して日用雑器を主体に今日まで焼き続けられており、灰釉や鉄釉などによる、素朴で飾り気がなく野趣味たっぷりな湯呑・皿・鉢・徳利・ぐい呑・壷・花瓶など「生活用器」の生産を身上としております。 ◆穴窯時代は自然釉 穴窯時代のやきものは、紐(ひも)づくりロクロ仕上げで、人工的な釉薬(ゆうやく)は使われず、穴窯の中で長時間焼かれることにより、燃えた薪の灰が焼成中に器に降りかかって、原土の中に含まれた鉄分と融け合い、緑色や鳶(とび)色を自然発色しました。 これが自然釉(ビードロ釉)といわれるもので、穴窯時代丹波焼の特徴となっています。 ◆窯変美の魅力 登り窯による焼成は約60時間続き、最高温度は1300度に達しますが、その結果燃料である松薪 の灰が器の上に降りかかり、釉薬と融け合って窯変し、「灰被り(はいかぶり)」と呼ばれる魅力的 な色や模様が一品づつ異なって表れるのが丹波立杭焼の大きな特徴で、このため実用だけでなく、観賞用としても愛陶家に広く知れ渡り、しかも作品の焼肌に慣れ親しむほど、さらに色合いや模様が変化し、趣をかえるのが、丹波立杭焼の真骨頂といえるでしょう。 |
| 沿道に建ち並ぶ窯元と登り窯 右手には緑の田圃が広がり、左手には、看板をぶら下げた窯元が点々と建ち並ぶ街道を歩いていると、突然登り窯が現れる。 和風のショウウィンドウの中には、それぞれの立杭焼が飾られ、旧街道と思われる細い道に入っても、窯元名の看板をぶら下げた家があり、その間にも登り窯を見つけることができた。 村の夏祭りがあるのか、あぜ道に沿って提灯が連なっていた。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |