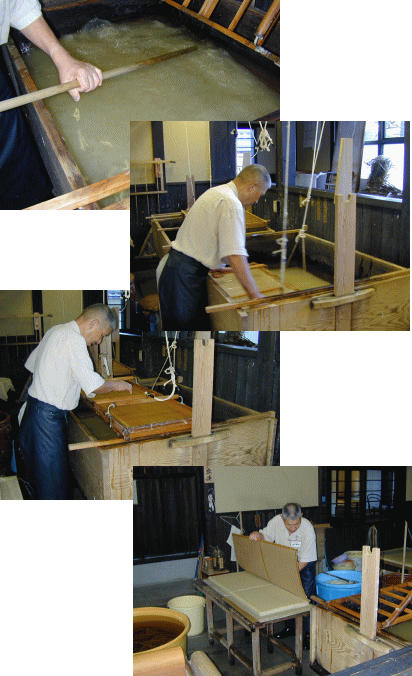|
和紙の里通り パピルス館と和紙の里会館の間に和紙の里通りがある。 通りに面して和紙漉きの実演を見ることの出来る卯建の工芸館と、越前和紙やその工芸品などの土産物を売る和紙の里があり、通りの両端には駐車場がある。 私が卯建の工芸館に入った時は、既に閉館間際だったのですが、紙漉の実演を見せておられる職人のおじさんが、とっても親切な方で、片付けの手を止めてまで、私の質問に答えていただき、紙を漉くところも見せていただきました。 数十年に渡っての紙漉で、指紋がなくなるほどツルツルになったおじさんの指先を見て、伝統の技を見た気がしました。 |
|
伝統の技 越前和紙が出来るまで ◆今立で作られる越前和紙の原料としては、楮・三椏・雁皮・麻である。 紙は繊維のあるものなら、なにからでもできるが、処理のしやすさ、できた紙の質と使いよさから考えて、これらに優る原料はない。 越前和紙千五百年の歴史から生まれた知恵である。 ◆楮は冬に刈り取り、蒸気で蒸す。 蒸し終わったら、すぐに冷水をかけて皮をはぐ。 はいだ皮の乾かしたものを黒皮という。 和紙は皮の繊維(靭皮)を用いる。 ◆水洗いした白皮を1〜2時間煮る。昔は草や木の灰から灰汁をとって煮たが、現在は木灰の代わりに、ソーダ灰や苛性ソーダで煮る。繊維がほぐれやすくするのと同じ時に、リグニンなどの紙に有害なものを除く作業である。 ◆煮た皮の灰汁を水で洗い流す。 いつも水が流れるようにした川小屋で、煮た白皮をかごに入れて、小さな塵や細かい節の汚れなどを洗いながら取り除く。 この作業を2回3回繰り返す。 これを「塵とり」、または「選る」という。 ◆塵とりの終わった皮を桜、または欅の木で作った叩き盤の上に乗せ、樫の木の角棒でトントンと叩いて繊維を解きほぐす。 この作業を「叩解」という。 叩いた皮を流れている水の中で念入りに洗って、澱粉質などの不純物を洗い流す。 これを「紙だし」という。 ◆糊空木の皮を煮て粘液を採る。 また、とろろあおいの根の部分を臼でついて粘液を採る。 これらの粘液を「ねり」という。 ねりは漉舟の中の原料(紙料)が早く沈まないよう浮遊度を高める働き、紙料が長く簀の上にとどまるようにする働きがあり、さらに漉きあげて重ねた紙と紙とが、乾燥する時に1枚ずつ容易にはがれるなど不思議な性質を持っている。 ◆紙の漉き方には溜め漉きと流し漉きがある。 溜め漉きは古代中国から伝わった紙漉き法で、金網を張った桁の上に紙料を1回ですくい上げ、桁を水平にして前後左右に細かく揺り動かして紙を漉く。 流し漉きは奈良時代の終わりから平安時代の初めに、ねりの発見とともに開発された日本独特の漉き方。 竹簀を張った漉桁で紙料を汲み上げては前後左右に揺すり、求める厚さになるまで汲んでは揺する。 ◆漉いた紙は、紙床板に重ねていく。 その紙床板をそのまま一晩水切りをした後、天秤を利用し重石をかけて徐々に圧力を加えて水分をしぼる。 ◆圧搾を終えた湿紙(紙床紙)を1枚ごとにはさんであるユガラ(い草)を手がかりにはがす。 そして、1枚ずつ保し板に刷毛で張付けて、紙を乾かす。 紙の風合い、肌合いを重んじる越前和紙は、雌いちょうの干し板を用いる。 乾燥すれば出来上がりである。 |
|