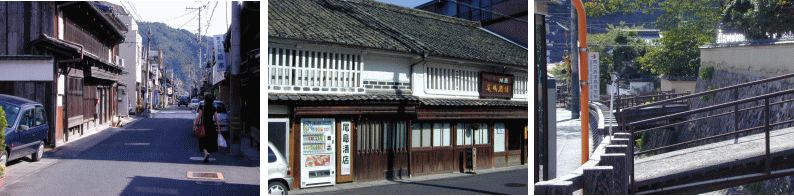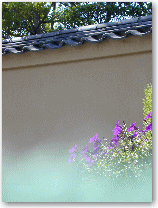 |
石火矢町は通りの両側に土塀が続き、明治維新以後130年以上になる今も、格式のある門構えの家並みが見られる武家屋敷町です。 現在、武家屋敷館として公開されている漆喰壁(しっくいかべ)の美しい建物は、今から170年前の天保(てんぽう)年間に建てられたもので、160石馬回(うままわ)り役を勤めた武士が住んでいたものです。 母屋(おもや)は格式のある書院造り、また中庭の池や庭石、踏み石などは、ほぼ昔のままで、その庭に面して資料館があります。
石火矢とは昔の大砲を意味し、鉄砲や大砲を持って出陣する武士達が、この界隈に集まって暮らしていたことに由来しているらしい。
|
 |