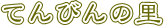
五個荘町は近江商人の発祥の地として広く知られ、白壁と舟板塀の蔵屋敷や優雅な庭園など、町内のいたるところで見ることが出来ます。
近江商人とは、近江に本拠地をおく他国稼ぎ商人のことで、近江八幡・日野・五個荘から特に多く輩出しました。 その中でも五個荘出身の近江商人を五個荘商人と呼んでいます。 五個荘商人はそのほとんどが江戸時代末期から明治時代の創業で現在も商社として多くの企業が活躍しています。
取扱商品は、呉服・太物・麻布など繊維関係が主で、活動範囲は関東・信濃・奥羽地方と畿内が中心でした。
五個荘商人の経営活動を支えていたのは勤勉・倹約・正直・堅実・自立の精神で先祖を大切に、敬神の念を常に忘れず、成功しても「奢者必心不久」「自彊不息」の心で、公共福祉事業に貢献したそうです。 |
 |
|