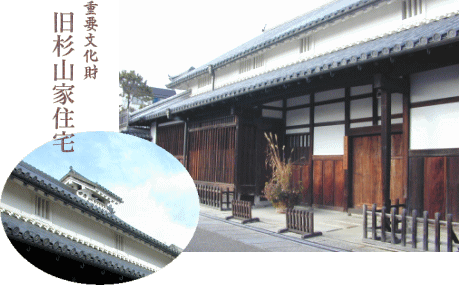
富田林寺内町の古い町家は整型四間取りの平面構成をとり、煙返しの梁など農家の建築技法を用いています。旧杉山家住宅はこれら町家の中で最も古い遺構であり、規模も大きく質のよい商家の住宅として、昭和58年12月26日重要文化財に指定されました。 |
杉山家は寺内町創立以来の旧家で、代々「杉山長左衛門」を名乗り、江戸時代を通じ富田林八人衆の一人として町の経営に携わってきました。
旧来の家業は明らかではありませんが、貞享2(1685)年に酒造株を取得した後は、造り酒屋として成功し、当初30石であった酒造石高は、元禄10(1697)年に104石、天明5(1785)年に1103石と著しい発展を遂げています。江戸時代の屋敷図によると、杉山家の屋敷地は町割の一画を占める広大なもので、その中に主屋を始め酒蔵、釜屋、土蔵など十数棟が軒を接して建てられており、その繁栄をうかがうことができます。
主屋の建築年代は、土間部分が17世紀中期で最も古く、その後に座敷や二階部分を増築し、延享4(1747)年ごろほぼ現状の形に整ったものと考えられています。
|