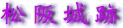
 |
 |
蒲生氏郷の築城になる平山城で、北東を大手、南東を搦手とし、本丸、二の丸、三の丸等よりなる。本丸、二の丸に高い石垣を築き、三の丸の周囲には土居と水堀が巡っていた。
元和5年(1619)松阪は紀州藩領となり、それ以後城内には藩の出先機関が置かれた。
本丸西隅の天守台には三層の天守が聳えていたが、正保元年(1644)大風により倒壊したと記録にあり、同じ頃の城絵図には敵見・金ノ間・太鼓・月見・遠見櫓が描かれている。
幅15〜31m、総延長2km余あった水堀は明治初期に埋められ、神道川等に名残りをとどめる。 |
|
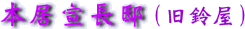
宣長が12歳のときから亡くなる72歳まで住居としていた家である。書斎の名を取って鈴屋(すずのや)と呼ばれる。 元は魚町にあったものを明治42年松阪城跡の現在地に移転し、庭園などは旧状を模し、若干の復元をして江戸時代の町家の姿を今に留めている。
間取りは、1階の見世の間、おいえの間、居間、仏間、奥座敷、台所、2階の書斎からなる。
書斎は、名声があがりはじめた53歳の時、物置を改造したものである。その床の近くに36個の鈴を掛けたことにちなみ、この書斎を鈴屋と命名した。宣長の主な著作はこの部屋で書かれたのである。
|
|
 |
 |

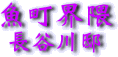 |
松阪は古くから高見峠を越して櫛田川沿いに和歌山街道が奈良県と連なり、参宮街道や伊賀・一志街道・熊野街道も集まり、歴史の古い地域でした。
蒲生氏郷が松阪城を築城する際に参宮街道を城下に縦貫させ江州の日野商人や松ケ島町民、角屋船の大湊人などを移住させ市場を開放(楽市)し、商品・商業ともに自由に営ませて、松阪商人発展の基を開きました。
紀州藩の積極的な保護奨励もあり、松阪商人の三井(越後屋)、小津、長谷川家など松阪木綿、松阪縞の販売で財をなした江戸店持ちの豪商の出身地とし、国学の大家本居宣長の名と共に全国に響いた。他にも大湊の廻船問屋角屋や射和の富山、国分家、中万の竹口家、相可の大和屋(西村)、大里屋(向井)、丹生の梅屋(長井)などが有名でした。当時、この地は交通の便が良く、大石紬(大石)、六保笠(機殿)軽粉、千熊味噌(射和)、壺屋紙といわれた擬革紙(漕代)など特産物のほか、茶(川俣茶・飯南茶)、和紙(深野)木材など近隣の飯南・多気・度会郡などの産物の集散地でもあった。 |
|


